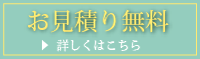2025.08.27 ヘクソカズラ(屁屎葛)
連日の酷暑と強い日差しにより、夏はどうしても花を見かける機会が少なくなります。 そんな折、弊社農業部の圃場にて、ブルーベリーの木に巻き付いてたくさんの花を咲かせているヘクソカズラに出会いました。 小さな花や蕾のかたち、蔦の伸び方がとても可愛らしく、ヘクソカズラを模したオーナメントやモビールなどの装飾品があれば素敵だろう…なんて思ってしまいました。 一方で、なんとも率直な和名の由来は、茎や葉を傷つけた時に感じる独特の匂いからだそうですが、個人的にはそれほどの臭いだとは思えません。 そこでふと、世界ではどのように表現されているのだろうと思い、調べてみました。 英名ではスカンク・ヴァイン(Skunk vine:スカンクの蔓)、スティンク・ヴァイン(Stink vine::臭い蔓)、漢名では鶏屎藤(けいしとう)と呼ぶそうで、さらには日本最古の和歌集『万葉集』にも「屎葛(くそかずら)」の名で詠まれていました。 …どうやら国や時代を問わず、この独特な匂いはあまり好まれてこなかったようです。 ただ、一部の地域では花の姿をとらえて「早乙女花(サオトメバナ)」「早乙女蔓(サオトメカズラ)」と呼ぶとのこと。実際に目の前で咲いている姿を見ていると、その呼び名のほうがしっくりくる気がします。 特徴をどう捉えるか…人による感覚の違いが、この花の名前に映し出されているように思います。